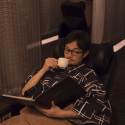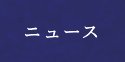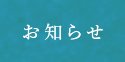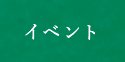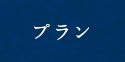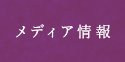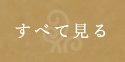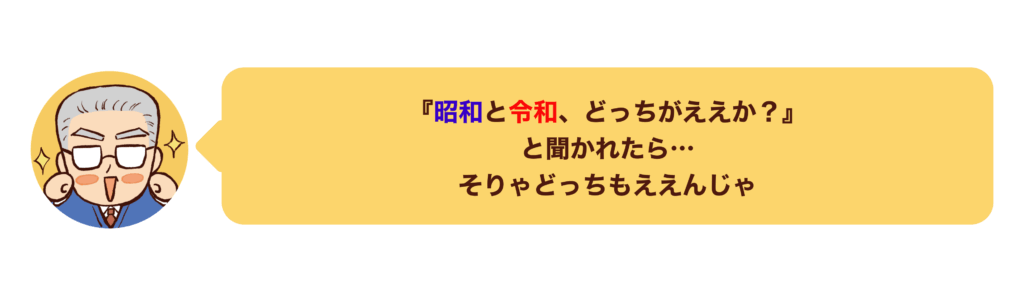
やあやあ、万葉おじさんじゃよ。
最近はもうすっかり定着した言葉に「ととのう」があるのう。
どうやらサウナに入って、身体と心が整ったときの感覚をそう呼ぶらしいんじゃが、わしの若い頃には、そんな言い回しはなかったもんじゃ。
時代は変わるのう。とはいえ、サウナというものはいつの世も、心と身体を整えるための場所じゃった――。
今日は、わしがこの目で見てきたサウナの“進化の物語”を、歴史の話から、昭和と令和それぞれのサウナの姿まで、少し語ってみようと思うとる。
サウナといえば、一般にはフィンランド発祥と言われておる。
木造の小屋で薪を焚いて石を熱し、水をかけて蒸気を発生させる――
そんな“ロウリュ”文化が、世界に広がっていったんじゃな。
日本に本格的にサウナが入ってきたのは、戦後まもない1950年代。
フィンランド式サウナが東京オリンピック(1964年)をきっかけに注目され、
徐々に健康施設やホテルなどに広がっていったというわけじゃ。
じゃが、日本にもそれ以前から“蒸し風呂”文化があったんじゃ。
奈良時代までは「釜風呂」や「石風呂」といった蒸気浴が主流で、
平安時代には「湯屋」が登場。
鎌倉〜江戸時代には外から蒸気を送り込む「蒸し風呂」へと移り変わり、
安土桃山から江戸初期には、蒸気とお湯を組み合わせた「半蒸気浴」が流行。
そして江戸中期以降、ようやく現代に近い「温湯浴」が一般化していったんじゃ。
つまり、日本人はずっと昔から「温めて癒す」という文化を大事にしてきた民族なんじゃよ。
わしらの身体には、もともとサウナの精神が馴染んでおるということじゃな。
わしが20代の頃――つまり昭和のサウナブームの時代は、
今のようなロウリュやアウフグースなんてものはなかったのう。
室内はカラッカラに乾いていて、ただただ暑い。
誰もしゃべらんし、テレビも音楽もない。
そんな中、黙って汗を流す。まさに“昭和ストロングスタイル”じゃった。
水風呂もなかったわけじゃないが、存在があまり知られていなかった。
汗をかいたらシャワーを浴びて、またサウナに入る――
そんなスタイルが当たり前だった。
それでものう、サウナはおじさんたちの「社交場」だったんじゃ。
誰が先に出るか出ないか、黙って駆け引きするような、
不思議な空気が流れていたのを覚えておる。
あの頃のサウナには、サウナなりの“緊張感”と“礼儀”があったのう。
そして時は流れて、令和の今。
今どきのサウナを見ると、驚くことばかりじゃ。
ロウリュで蒸気を楽しみ、アウフグースで熱波を浴び、水風呂からの外気浴で“ととのう”――
まるでひとつのアクティビティのように、若者たちの間で楽しみの文化として根づいてきておる。
冷たいサウナドリンクや、サウナ飯なるものもあって、
わしの時代には想像もつかん賑やかさじゃよ。
でも、よく観察してみると、今の若者たちはサウナを
単なる“汗をかく場”ではなく、“自分をリセットする場”として楽しんどるように見える。
漫画やSNSを通じてサウナの魅力が広まり、
「1セット10分」とか「ととのい椅子」といったルールも共有されていて、
サウナが“アクティビティ”として社会に根付いているのを感じるんじゃな。
わしが思うに、サウナ文化は「熱くて乾燥してる場」から
「湿度もあって、健康にもよく、心まで整う場」に進化してきたんじゃ。
スマホを置いて、誰ともしゃべらず、ただ自分の内側と向き合う――
これはまさに“デジタルデトックス”とも言える時間じゃな。
昔ながらの昭和サウナにも、今の令和サウナにも、それぞれの良さがある。
だからこそ、わしもまだまだ修行中じゃ。
“ととのい”という言葉は、最初はよく分からんかったが、
今は分かるようになってきた気がする。
サウナの本質は、いつの時代も“自分を整える場所”なんじゃな。
そして――
8月1日から、全国の万葉の湯・万葉倶楽部10館合同サウナ応援キャンペーン「ととのいの夏!万葉でサ活」が始まるんじゃ!
サウナ飯や、オリジナルグッズなどこの夏だけの“ととのい”体験が、各館で味わえるぞい。
わしももちろん、参加する予定じゃ。
次回は、“ととのう”ための入り方を、わしなりに詳しく語ってみようかのう。
楽しみにしておるぞい!